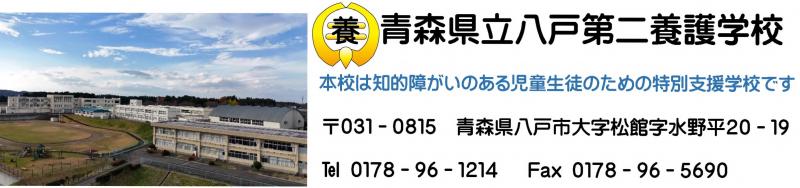学習活動の様子をお知らせします!
八二養の日々
サッカー教室
ヴァンラーレ八戸さんを招いてサッカー教室が行われました。
中学部の生徒は、この日を心待ちにしていました。
グラウンドから大きな掛け声が聞こえてきました。
手をつないで大きな輪になって「ま~え」、「うしろ」、「み~ぎ」、「ひだり」の声に合わせてジャンプしています。
最初は、掛け声通り、最後は掛け声とは逆に(「み~ぎ」と言いながら左へジャンプ)。

簡単!簡単!と自信満々だった生徒たちも、最後は動きがガタガタに・・・
その難しさに必死になるのもまた楽しいようでした。
こういった抑制機能(簡単に言うと余計な刺激に反応しないようにする)を使う課題は、難しいけど楽しいものです。
鈍くなった私たち大人より、子供の方が上手くできることもあり、真剣勝負ができて一緒に楽しめます。おすすめです。
本校の先生たちも、学習の中で、ちょっと難しいけどチャレンジしたくなる課題を上手にセレクトして準備しています。
この視点は、子供たちと一緒に楽しく学習する上でとても大切な視点なんだなと改めて思いました。
さて、準備運動は続きます。
背面キャッチ ドリブル シュート練習



そして、いよいよ試合。
第1試合 黄VS緑 第2試合 ヴァンラーレ八戸VS中学部


どちらの試合も熱戦でしたが、一番盛り上がったのは右の写真の場面。
ヴァンラーレ八戸からゴールを奪った瞬間です。全員が両腕を突き上げて喜びを爆発させていました。
生徒同士の対戦ではそこまでの歓喜はありませんでした。
やはり、格上と認めている相手からゴールを奪うことはこの上ない喜びなのでしょう。
とてもよい瞬間を演出してくれたヴァンラーレ八戸の皆さんに感謝したいと思います。
中学部の生徒は、この日を心待ちにしていました。
グラウンドから大きな掛け声が聞こえてきました。
手をつないで大きな輪になって「ま~え」、「うしろ」、「み~ぎ」、「ひだり」の声に合わせてジャンプしています。
最初は、掛け声通り、最後は掛け声とは逆に(「み~ぎ」と言いながら左へジャンプ)。

簡単!簡単!と自信満々だった生徒たちも、最後は動きがガタガタに・・・
その難しさに必死になるのもまた楽しいようでした。
こういった抑制機能(簡単に言うと余計な刺激に反応しないようにする)を使う課題は、難しいけど楽しいものです。
鈍くなった私たち大人より、子供の方が上手くできることもあり、真剣勝負ができて一緒に楽しめます。おすすめです。
本校の先生たちも、学習の中で、ちょっと難しいけどチャレンジしたくなる課題を上手にセレクトして準備しています。
この視点は、子供たちと一緒に楽しく学習する上でとても大切な視点なんだなと改めて思いました。
さて、準備運動は続きます。
背面キャッチ ドリブル シュート練習



そして、いよいよ試合。
第1試合 黄VS緑 第2試合 ヴァンラーレ八戸VS中学部


どちらの試合も熱戦でしたが、一番盛り上がったのは右の写真の場面。
ヴァンラーレ八戸からゴールを奪った瞬間です。全員が両腕を突き上げて喜びを爆発させていました。
生徒同士の対戦ではそこまでの歓喜はありませんでした。
やはり、格上と認めている相手からゴールを奪うことはこの上ない喜びなのでしょう。
とてもよい瞬間を演出してくれたヴァンラーレ八戸の皆さんに感謝したいと思います。
小学部5年宿泊学習
本校では、3年ぶりに宿泊を伴う行事が行われ、小学部5年生が学校に宿泊しました。
宿泊するということで、普段の学習以上に感染拡大防止に気を遣いましたが、保護者の皆さんにも、普段以上の細やかな体調観察等をしていただき、私たちも安心して臨むことができました。
一緒に泊まってみての感想は、一言「やってよかったな。」です。
子供たちは、宿泊の前から「8日は泊まるんだよ。」「先生も泊まるんでしょ。」と楽しみにしている様子でした。布団を敷く学習をしたり、日程や活動内容を教えてもらって自分の役割を確認したりしながら準備を進める中で期待感がどんどん高まっているようでした。
宿泊当日の夜の様子です。


けんか??いえいえ、表情を見てください。とっても楽しそうです。
布団を敷くと気持ちがウキウキして友達と密着したくなります。
気持ちが高ぶって眠れないかな?と心配しましたが、ほどよく疲れたのがよかったのか、9時にはぐっすり就寝。
翌日は、朝から元気に布団運び。みんなよく働きます。

「青春は密」と言った高校野球の監督さんがいましたが、宿泊学習の2日間はまさにそういう感じ。
距離も、経験も密な宿泊学習でした。
でも、距離的な密は短時間でね、と言わなければならないつらさ・・・。
早く、思う存分「密」を経験させてあげられるようになればいいなと思います。
宿泊するということで、普段の学習以上に感染拡大防止に気を遣いましたが、保護者の皆さんにも、普段以上の細やかな体調観察等をしていただき、私たちも安心して臨むことができました。
一緒に泊まってみての感想は、一言「やってよかったな。」です。
子供たちは、宿泊の前から「8日は泊まるんだよ。」「先生も泊まるんでしょ。」と楽しみにしている様子でした。布団を敷く学習をしたり、日程や活動内容を教えてもらって自分の役割を確認したりしながら準備を進める中で期待感がどんどん高まっているようでした。
宿泊当日の夜の様子です。


けんか??いえいえ、表情を見てください。とっても楽しそうです。
布団を敷くと気持ちがウキウキして友達と密着したくなります。
気持ちが高ぶって眠れないかな?と心配しましたが、ほどよく疲れたのがよかったのか、9時にはぐっすり就寝。
翌日は、朝から元気に布団運び。みんなよく働きます。

「青春は密」と言った高校野球の監督さんがいましたが、宿泊学習の2日間はまさにそういう感じ。
距離も、経験も密な宿泊学習でした。
でも、距離的な密は短時間でね、と言わなければならないつらさ・・・。
早く、思う存分「密」を経験させてあげられるようになればいいなと思います。
総合的な学習の時間に「本物」の世界へ
中学部の教室に用事があって、階段を上っていくと・・・

びっくりして、一瞬頭が混乱し、引き返そうかと思ってしまいました・・・。
制作者は、八戸三社大祭の山車作りに携わっている本校の先生です。
発泡スチロールの板を貼り合わせて、そこから削り出し、細かい部分は紙粘土で整えているのだそうです。
やはり本物の迫力は違いますね。
構えなしに見ると大人でもたじろいでしまうぐらいですから。
近くにいた先生に話を聞くと、総合的な学習の時間の中で「八戸三社大祭」について学習したときに使わせていただいたのだそうです。
見たり、触ったり、一緒に写真を撮ったり。
コロナ禍では、直接見に行く、触れるという機会は限られてしまいますから、生徒たちにとって久しぶりの「本物」に触れる学習になったのではないかと思います。
本校には、こうした「本物」を伝えられる先生がたくさんいます。
まさに人材の宝庫です。
ぜひ学習活動の中で持ち味を存分に発揮して、子供たちを「本物」の世界へ連れて行ってほしいと思います。

びっくりして、一瞬頭が混乱し、引き返そうかと思ってしまいました・・・。
制作者は、八戸三社大祭の山車作りに携わっている本校の先生です。
発泡スチロールの板を貼り合わせて、そこから削り出し、細かい部分は紙粘土で整えているのだそうです。
やはり本物の迫力は違いますね。
構えなしに見ると大人でもたじろいでしまうぐらいですから。
近くにいた先生に話を聞くと、総合的な学習の時間の中で「八戸三社大祭」について学習したときに使わせていただいたのだそうです。
見たり、触ったり、一緒に写真を撮ったり。
コロナ禍では、直接見に行く、触れるという機会は限られてしまいますから、生徒たちにとって久しぶりの「本物」に触れる学習になったのではないかと思います。
本校には、こうした「本物」を伝えられる先生がたくさんいます。
まさに人材の宝庫です。
ぜひ学習活動の中で持ち味を存分に発揮して、子供たちを「本物」の世界へ連れて行ってほしいと思います。
バージョンアップ!全校集会
本校では今日から授業が始まり、全校集会が行われました。

これまでは、放送と事前撮影した動画を活用して行っていましたが、今回からWEB会議システムを使って、体育館の様子を各教室に配信する形で行われました。
リアルタイムで顔が見える形というのは、画面越しとはいえ、臨場感が違います。


話している方も、放送や事前に動画撮影するのとは違って、カメラの向こうにいる子供たちを意識した語りになっているように感じました。


今日の集会の中では、保健部の先生から給食が作られる様子、配膳、後片付けまでの仕事の流れが紹介されました。
様々な機械が動く様子に子供たちも、先生たちも釘付けでした。私もこんなにすごい設備が本校にあったのかと新しい発見をしました。
子供たちは働いている大人たちの手際のよさを見て驚いている様子でした。中には拍手をしながら見ている子もいました。私たちの想像を超える「すごい仕事」をしているんだと感じたのかもしれません。私もその気持ちが分かります。
今日のお話を通して、知らないところで私たちの生活を支えてくれている人がたくさんいるのだということに気が付いてくれたら嬉しいですね。
さて、本校では、市内の小中学校より少し早く夏季休業明けの学習がスタートしました。
時々、なんで早いの?と聞かれるのですが、それは本校の児童生徒の登校方法と関係があります。
ほとんどの子供がスクールバスを利用して登校しているのですが、冬になると道路事情から授業開始が遅れることが多々あります。そこで、冬季休業に入る日を少しでも早くし、その分夏に授業をする方が授業時数を確保できるということからそのような工夫をしています。
(曜日の関係から毎年そういう工夫ができるとは限りませんが、できるだけそうしたいと思って組み立てています)
夏に授業日を増やすのは、エアコンを設置していただいたからこそできる工夫でもあります。有り難いですね。

これまでは、放送と事前撮影した動画を活用して行っていましたが、今回からWEB会議システムを使って、体育館の様子を各教室に配信する形で行われました。
リアルタイムで顔が見える形というのは、画面越しとはいえ、臨場感が違います。


話している方も、放送や事前に動画撮影するのとは違って、カメラの向こうにいる子供たちを意識した語りになっているように感じました。


今日の集会の中では、保健部の先生から給食が作られる様子、配膳、後片付けまでの仕事の流れが紹介されました。
様々な機械が動く様子に子供たちも、先生たちも釘付けでした。私もこんなにすごい設備が本校にあったのかと新しい発見をしました。
子供たちは働いている大人たちの手際のよさを見て驚いている様子でした。中には拍手をしながら見ている子もいました。私たちの想像を超える「すごい仕事」をしているんだと感じたのかもしれません。私もその気持ちが分かります。
今日のお話を通して、知らないところで私たちの生活を支えてくれている人がたくさんいるのだということに気が付いてくれたら嬉しいですね。
さて、本校では、市内の小中学校より少し早く夏季休業明けの学習がスタートしました。
時々、なんで早いの?と聞かれるのですが、それは本校の児童生徒の登校方法と関係があります。
ほとんどの子供がスクールバスを利用して登校しているのですが、冬になると道路事情から授業開始が遅れることが多々あります。そこで、冬季休業に入る日を少しでも早くし、その分夏に授業をする方が授業時数を確保できるということからそのような工夫をしています。
(曜日の関係から毎年そういう工夫ができるとは限りませんが、できるだけそうしたいと思って組み立てています)
夏に授業日を増やすのは、エアコンを設置していただいたからこそできる工夫でもあります。有り難いですね。
ツバメを見守る気持ち
学校の玄関にツバメの巣があります。
ツバメは、天敵から身を守るため、人の出入りのある場所に巣を作るそうです。
それも自分たちに危害を加えることがない優しい人のそばに!
子供たちも、私たち大人も、朝学校に来たとき、帰るとき、ツバメの巣を確認し、成長を見守ってきました。ツバメの巣を棒でつついたり、ものを投げたりする子など一人もいません。優しい子供たちです。
そんな安全・安心な環境の中ですくすくと育った雛は親鳥と同じぐらいに大きくなり、巣からはみ出しそうになりながら、えさを待っています。子供たちが夏休みの間に巣立っていく気配です。
夏休みが明けて登校してきた子供たちはがっかりするかもしれませんが、「みんなが優しく見守ってくれたから大人になって飛んでいったんだよ。」と教えてあげたいと思います。
ツバメを見守った自分たちの思いに気付くことで、保護者の皆さんが自分のことを見守る気持ちにも思いを巡らせてくれたらいいなあと思います。自分を見守ってくれる人の存在を意識することは成長の大きな力になりますからね。
アクセスカウンター
7
6
7
3
1
0
2
お知らせ
電話対応時間について
(職員、保護者以外の方へ)
本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。
電話対応時間
平日 8:20~16:50
休日 電話対応を行いません。
上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。
後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。
リンク集
新着