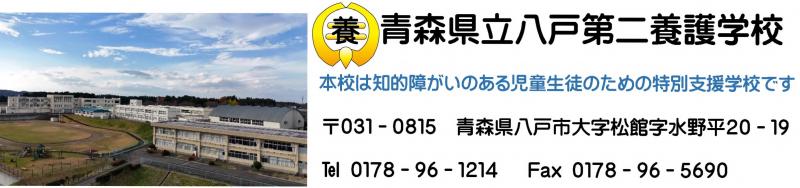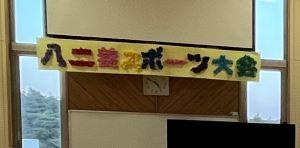八二養の日々
農業体験 田植え
5月22日(水)に小学部のいくつかの学級が田植えの体験をしました。
地域とのつながりを大切にしながら、地域の教育的資源を活用した取り組みです。
子供たちにとっては素足で田んぼに入るところから始まり、初めて経験することばかりだと思います。
教頭先生が撮影した400枚以上の写真には、説明を聞く真剣な表情、泥の感触に戸惑う表情、小川の水の冷たさに
びっくりした表情、何より楽しそうに笑っている表情がたくさん写っていました。
苗の持ち方や植え方を聞いています。
先生と一緒に実際に植えてみよう。
一人で実際に植えてみよう。
近くの小川で泥だらけの手と足を洗いました。
子供たちにとって思い出に残る、貴重な体験になったと思います。
全校一斉の 災害時保護者引き渡し訓練
5月14日(火)に災害発生を想定した保護者引き渡し訓練を実施しました。
コロナ禍では、待機場所を分散したり時間差で引き渡したりと工夫しながら実施してきましたが、今回は、児童生徒全
員が体育館で待機して保護者を待ちました。継続的に避難訓練に取り組んでいることもあり、児童生徒が落ち着いて体育
館への移動したり迎えを待ったりしている様子に感心させられました。
先生の話を聞いて待機しています。
保護者も待っています。
保護者の皆様、御協力ありがとうございました。
多くの保護者が来校 全校参観日・PTA総会
5月2日(木)に全校参観日・PTA総会を行いました。
200名以上の保護者が来校し、子供たちの学習の様子を参観しました。
張り切っていた子、ちょっと緊張気味だった子と子供たちの表情や様子もいろいろでした。
小学部1年生の音楽「音楽で仲良くなろう」
小学部3年生の体育「集まろう・走ろう」
全体会とPTA総会
児童生徒の学校生活や学習の様子を見ていただく機会。また、学校や各学部の方針について知っていただく機会となりました。
一年間、教育活動への御理解と御協力をお願いします。
ようこそ八二養へ 歓迎会
小学部の歓迎会は4月26日(金)、中学部の歓迎会は4月22日(月)にどちらも体育館で行われました。
小学部は、「1年生入場」「1年生の紹介」そしてみんなで「手遊び」や「ダンス」をしました。
1年生は友達や教師と一緒に楽しく活動し、2・3年生は準備や当日の役割を通して1年生を迎える気持ちを
もち活動することができたと思います。
友達や先生と一緒に入場です。
学級ごとに自己紹介をしました。
中学部は「新入生入場」から始まり「校長先生のお話」「1年生の発表」「歌のプレゼント」「ゲーム」
「プレゼント贈呈」・・・。2・3年生が新入生を歓迎する気持ちをもち、歓迎会の内容を考えたり事前の
準備をしたりしました。
「校長先生も木村教頭先生も(この学校に赴任したばかりの)1年生です。」
自己紹介で好きな食べ物や好きなことを発表しました。
「八二養ウルトラクイズ」開催! 〇かな?✕かな?
春の学習 交通安全教室
春の学習活動で思い浮かぶのは「交通安全教室」ですよね。
本校では、小学部1~3年、小学部4~6年、中学部に分かれて実施しています。
登校時は、スクールバス9台と送迎サービスの車、保護者さんの車が時間差で駐車場に入ります。また、下校時はスクールバス6台、施設さんの車が多いときで40台、そして保護者さんの車が出発します。
ですので、学校敷地内で使用する手作りの信号や交通ルールがあり、それらもみんなで確認しながら交通安全教室を実施します。
【小学部1~3年(体育館)】
1年生は、先生と一緒にやってみよう!
2年生は、一人で挑戦してみよう!
【小学部4~6年(屋外)】
児童生徒玄関前の横断歩道で練習しよう!
実際に学校前の横断歩道を渡ってみよう!
【中学部(屋外)】
5/8(水)実施予定
暖かくなり、校外での活動も多くなります。みなさん交通ルールを守りながら安全に活動しましょう。
1回目の 全校集会
4月15日(月)の2時間目に、全校児童生徒が集まっての全校集会を行いました。
1回目は、①校長先生の話、②生徒会の自己紹介、③新任者の自己紹介(中学部)という内容です。
校長先生からは、
1 あいさつをしよう
2 目標を決めよう
3 家族や友達と仲良くしよう
の3つのお願いがありました。子供たちも先生方も頑張りましょう。
一年間よろしくお願いします。
皆さん、先生方の名前を覚えて、元気に挨拶したり、一緒に活動したりしましょう。
小・中学部が一緒に 入学式
4月9日(火)に入学式が行われました。
5年ぶりに全校児童生徒が体育館に入り、小学部新入生17名、中学部新入生25名の入学をお祝いすることができました。
生徒会長の「歓迎の言葉」には
「たくさんの友達や、先生たちと一緒に勉強をしたり、遊んだりし て、楽しい思い出がたくさんできるので安心してください。私たちと一緒に、素敵な思い出を作っていきましょう。分からないことがあれば、なんでも聞いてください。」
という優しくて心強い言葉がありました。
新入生の皆さん、先輩や友達、先生がそばにいます。安心して学校生活を送ってください。
八二養全校児童生徒199名がそろってのスタートです。
令和6年度がスタート 新任式・始業式
4月8日(月)に新任式・始業式が行われ、今年度がスタートしました。
新任式では、新任職員26名の紹介があり、代表して校長先生からの挨拶がありました。
また、始業式では、転入生3名の紹介がありました。ステージ上での自己紹介は、少し緊張した様子でしたが大きな声で名前を言うことができました。
児童生徒の皆さん、新しい友達、新しい先生の名前を覚えて、一年間楽しく学習活動に取り組みましょう。
令和5年度 卒業式
本日、4年振りに小学部・中学部が一緒に卒業式が行われました。
卒業生一人一人がステージに上がり、御来賓の皆様、保護者の皆様に見守られるなか、校長より卒業証書が手渡されました。
卒業生はみんな自信に満ちあふれており、これからの生活に期待をしているように見えました。
改めて、人生の節目で人は大きく成長できると実感しました。
卒業生の皆さん本当に御卒業おめでとうございます。
えんぶり鑑賞会
鳥屋部えんぶり組を本校にお招きして、第29回えんぶり鑑賞会が行われました。
4年振り対面での鑑賞会なので子供たちも先生方も楽しみにしていました。
初めてのえんぶりに興味を示し前のめりになって鑑賞する子、おはやしや舞のリズムに合わせて体を動かしている子、タイが釣れると立ち上がって喜びを表す子などそれぞれ見て、聞いて、感じて楽しむことができました。
最後に質問コーナーがありました。
4人が感想を話したり質問したりしました。
3社の新聞等の取材があり、代表の生徒たちがインタビューに答えていました。よい経験でしたね。
今回の司会は、中学部の新生徒会役員の皆さんが担当してくれました。司会デビューでしたが、ハキハキ堂々と話してをしていました。
最後に新生徒会長からお礼の言葉がありました。
2月17日から八戸えんぶりが始まります。
みなさんも、八戸えんぶりを見に、出掛けてみてはいかがでしょうか。
全校集会
1月15日全校集会がありました。
長い冬休みを終えた児童生徒が体育館に集まりました。
教頭先生のお話の中で、大谷選手から送られたグローブの紹介がありました。箱からグローブを取り出すと歓声があがりました。
集会後、近くで見たり触ったりしている児童生徒がたくさんいました。
次に生徒会役員に当選した人の紹介がありました。
中学部の新生徒会長と新生徒会副会長2名の自己紹介がありました。
令和6年度活躍を期待しています。
スポーツ大会をふりかえろうでは、スポーツ大会のスライドショーがスクリーンに映し出さると、児童生徒は真剣に見入っていました。
小学部・中学部の発表
楽しかった冬休みの様子を発表しました。
最後のエイエイオーは小学部1年4組と3年5組が担当でした。
1月から3月は、本校ではえんぶり鑑賞会やお別れ会、卒業式など行事がたくさんあります。また1年をまとめる大切な時期でもあります。寒い日が続きますが、体調に気を付けて元気に過ごして欲しいと思います。
作品展のお知らせ
第43回八戸第二養護学校作品展が
1月13日(土)~15日(月)に
ラピア フェスタプラザ(1F)で行われます。
ぜひ、足をお運びいただき、児童生徒の作品をご覧ください。
全校集会
本日、冬休み前の全校集会が行われました。
冬休みの過ごし方について話がありました。
休み中の生活で守ることを確認できました。
次に作品展の話がありました。
今年度もラピアで1月13日から1月15日までの日程で行われます。
最後は、八二養恒例の「エイエイオー」です。
担当は小学部6年4組でした。
明日からいよいよ冬休み。
冬休みの楽しみはたくさんあると思います。
自分の楽しみが一つでも叶うといいですね。
音楽鑑賞会
冬休みが間近に迫った本日、自衛隊北部航空音楽隊をお招きして音楽鑑賞会が行われました。
今年度は、前半小学部、後半中学部と分けての実施となりました。
【前半の小学部】
児童は椅子を持って体育館に集まってきました。久しぶりの生演奏の音楽鑑賞会からなのか、制服を着た演奏者40名ほど目の前にしたからなのか、児童の多くはとても緊張をした様子でした。
演奏が始まると、手拍子をしたり、体でリズムをとったりと楽しんでいる様子に変わりました。
知っている曲が聞こえてくると、椅子から落ちそうになるほど体を左右に動かしたり、思わず立ち上がってジャンプしたりして盛り上がりました。
指揮者体験を、6年生の代表児童が行いました。音楽隊の指揮者から指揮のポイントを教えていただいた後、実際に指揮をしました。
ゆったりと腕を大きく動かして指揮をしていました。曲の最後には、持っていた指揮棒をピタッと止めることができ、会場から大きな拍手をもらいました。
【後半の中学部】
1曲目が始まると、すぐに演奏に引き込まれるように真剣に聞いている表情が印象的でした。音楽隊の指揮者が手拍子を促すと生徒はそれに応じると同時に表情が少し和らぎ、音楽を楽しんでいました。
最後に音楽隊の「ゆかいなお兄さんお姉さん」のダンスに合わせて、生徒もダンスをしました。隣の友達とぶつからないように少し遠慮しながらもダイナミックな動きでダンスをしていました。
近年はコロナ渦ということもあり、生の演奏に触れる機会がありませんでした。大勢での生の演奏を聴いた、児童生徒の目の輝きがより美しく見えました。
私たち教員は、これからも児童生徒がわくわくドキドキして、学んでいけるような計画をたくさん用意していきたいと思いました。
生徒会役員選挙(中学部)
先日、中学部生徒会役員選挙がありました。
選挙管理委員は中学部3年生が担当し、今年度は会長、副会長ともに複数名が立候補しました。
候補者は、ポスターを掲示し、選挙運動や立会演説会では「清き一票」をお願いしていました。
そして投票が行われました。
地域の投票所で戸惑わないように、本校の役員選挙では、八戸市選挙管理委員会からお借りした、記載台と投票箱を使っています。
投票所入場券をもって生徒が体育館に集まってきました。
中3の係の生徒が入場券を確認し、事前に準備された名簿にチェックして、投票用紙を渡していきます。
投票用紙に自分が選んだ候補者の名前を記入します。
そして、投票箱に入れます。
2年生、3年生は一度は経験をしているので、先生の支援がなくても自分で投票することができます。
このように実際に経験して、選挙の仕組みや投票の仕方を学んで身に付けていきます。
18歳になると、地域の投票所で投票することができます。そのときにも今回の経験を生かして、自信をもって投票して欲しいと思っています。
南郷小学校との交流
先日、本校小学部4~6年生は、南郷小学校4年生を本校にお迎えして交流会を行いました。
活動1は、学年交流会です。
4年生のダンス「あおうえおんがく」の様子です。
会場いっぱいに広がって楽しくダンスをしました。
5年生のボッチャの様子です。
5チームに分かれてプレーし、得点が高い人がメダルをもらっていました。
6年生のダンス「ミックスナッツ」の様子です。
担当の先生からダンスのポイントを教えてもらい、ハイテンポの曲に合わせて笑顔で踊っていました。
活動2は、全体交流会です。
司会担当は、本校小学部6年生児童でした。
ハキハキとした進行で会を進めていました。
本校の発表の様子です。
グループに分かれて、器楽や歌、ダンスなどを発表しました。
南郷小学校の発表の様子です。
南中ソーランと合唱を発表してくれました。
感想発表の様子です。
本校代表児童代は、表楽しかったことや感じたことをを立派に発表することができました。
今回の交流会は、小学部の高学年らしく主体的に会を進め、集中して仲間の発表を見て、手拍子をしたり、発表後の拍手をしたりしている姿が印象的でした。
今回の交流会のために本校の児童が力を合わせて製作した横断幕です。
本校で製作する横断幕は、いつも丁寧で心が込めているなと感じています。きっと他校の皆さんとの交流を本当に楽しみにしているからだと思います。
階上小学校との交流
本校小学1~3年生は、階上小学校と交流をしています。
今年度は、階上小学校の皆さんを本校にお招きして交流することができました。
まずは学年に分かれての交流です。
1年生は、手遊び「グーチョキパーでなにつくろう」、ダンス「ラーメン体操」、ゲーム「たまいれ」を行いました。
2年生は、手遊び「さあみんなで」、ゲーム「玉入れ」を行いました。
3年生は、ダンス「ラーメン体操」ゲーム「ふたりではこぼう!」を行いました。
最後に体育館に集合し全体交流をしました。
代表の児童は分担しながら司会をがんばりました。
階上小学校のみなさんのダンスと合唱です。
最後にみんなでマイムマイムをしました。
本校でも何度か学習や集会等で経験があります。
とってもきれいな円を作ることができました。
曲が流れて、進む方向や前後に動くタイミングもしっかりと覚えて踊れました。
曲が終わると、両校の児童の笑顔と歓声が体育館にあふれました。

低学年らしさを感じた心温まる会となりました。
2023/10/18 スポーツ大会(中学部)
今回は中学部のスポーツ大会の様子をお届けします。
中学部はプライフーズスタジアム(八戸市多賀多目的運動場)において実施しました。
晴天の空の元、ヴァンラーレ八戸の選手とサッカーを行いました。
親子、兄弟、先生でチームを組んでヴァンラーレ八戸と熱戦を繰り広げ、みんなが夢中になってボールを追いかけました。
ヴァンラーレ八戸のマスコットキャラクター、ヴァン太くんも応援に来てくれました。
サッカーをするだけではなく、普段は入ることができない施設内を見学することができました。
記者会見やヒーローインタビューを行う場所で記念撮影をしました。
昼食の弁当も、おいしくいただきました。
閉会式では、ヴァンラーレ八戸の選手からエールをいただき、その後に代表生徒によるお礼の言葉を伝えました。
生徒、家族、先生がワンチームとなってヴァンラーレ八戸の選手とサッカーをすることで、仲間や家族の絆が深まったように感じます。
みなさん、とてもいい笑顔でした。
参加してくださった保護者の皆様、シーズン期間にもかかわらず歓迎してくださったヴァンラーレ八戸の皆様、ありがとうございました。
2023/10/17 スポーツ大会(小学部)
10月14日(土)に令和5年度スポーツ大会が行われました。
今年度は、小学部は校内で、中学部はプライフーズスタジアム(八戸市多賀多目的運動場)で実施しました。
今回は小学部の様子をお届けします。
児童が製作した横断幕
3つのメイン会場それぞれに飾られました。
スポーツ大会の目的は、「スポーツをする楽しさを味わい、最後までやり遂げる」「スポーツを通じて仲間と協力し、活動に意欲をもって取り組む」「スポーツを通じて保護者に児童の成長を知っていただく」「保護者と一緒にスポーツに親しむ」などです。
運動会と大きく違うのが4つめの「保護者と一緒にスポーツに親しむ」だと思います。前回(令和3年度)は、コロナ禍ということもあり児童だけでのスポーツ大会となってしまいましたが、今回は兄弟・姉妹、父母・祖父母も参加してのスポーツ大会となりました。
児童代表による選手宣誓
みんなでラジオ体操
保護者や兄弟も一緒にやりました。
小学部では、フライングディスク、ボッチャ、サッカーをそれぞれ簡素化した種目にお家の方と一緒に取り組みました。
○サッカー「サッカーボウリング」
サッカーボールを蹴って、10本のボウリングのピンを倒します。
○ボッチャ「チャレンジボッチャ」
ボッチャボールを八角的に投げて、得点を競います。
○フライングディスク「的宛てディスク」
ディスクを投げて、10本のペットボトルを倒します。
スタンプラリー形式で各種目を回り、いろいろな競技に取り組みました。今までであればお家の方には観戦や応援をお願いしていましたが、競技に参加していただくことでスポーツの楽しさをお子さんと一緒に感じていただくことができたと思います。
次回は中学部の様子をお届けします。
2023/09/29 安全運転の願い!
本校は県道11号線に隣接していて、
交通量が多く、信号が少ないため、スピードが出やすい箇所でもあります。
県道には歩道が整備されており、本校の児童生徒は、歩いて校外学習に出かけたり、散歩等で頻繁に使っています。
そのようなことから
横断幕やのぼり旗を設置し、ドライバーなどに安全運転をお願いしております。

そののぼり旗が新しくなりました。
カーブのぼりといわれる今人気の形です。
こののぼり旗によって、みなさんが安全運転していただければと願っています。
なお、こののぼり旗の劣化が少しでも遅くなるようにと、係の先生が夕方に土台から外して校内で保管しています。係の先生、お疲れさまです。
電話対応時間について
(職員、保護者以外の方へ)
本校では、職員の勤務時間外における電話対応を下記のように変更いたします。
電話対応時間
平日 8:20~16:50
休日 電話対応を行いません。
上記対応時間以外は、後日電話をかけ直していただくか、下記URLを読み取って①所属、②氏名、③連絡先電話番号、④連絡を取りたい本校職員名、⑤要件の概要を入力してください。
後日、職員から折り返しの電話をさせていただきます。